
着飾るのが好きだ、という人は多い。
好きではないという人もいるにはいるが、話を聞いてみれば着脱の面倒さや堅苦しさ、着飾っても出かける場所がないという憂鬱さ、どうせ自分には似合わないというネガティブな感情、もしくは金銭面の問題などに理由があったりする。そういう人だって自分の許容範囲内でそれなりに装っている筈なので、『純粋に自分が綺麗だと思うような服や装飾品を身につけるという行為、それそのものが我慢ならないんです』という人は滅多にお目に掛かれない。そういう例外もいるにはいるが、『美しく装いたい』というのはほぼ万人に共通する欲求であると言っていいのではないだろうか。
一方、着飾らせるのが好きだ、という人もいる。
彼らは自分が着飾るのが嫌いという訳でもないのだが、それ以上に着せたがる。誰かと連れ立ってショッピングなどにいっても、気がつけば連れの体に服をあてがって『○○ちゃんかわいーい』とか『おっ、これ似合うぞお前』とか言って喜んでいるタイプ。女性に多いイメージがあるが、男性にもいる。しかし男性のそれは主に特別な関係にある女性に対して発揮されることが多いのに対し、女性のそれは相手を選ばない。思うに、幼い頃着せ替え人形で遊んだときの様な気持ちが蘇っているのであろう。もしくは、自分好みの服だが自分で着ては服がよく見えない為、取り敢えず手近な人に着せて心行くまで眺めたい、なんて気持ちもあるかもしれない。残る可能性としては嫌がらせ(男性に女装を迫ったり)などもあるかもしれないが、今回はそういう話ではない為それは割愛する。
さて、前置きが長くなったが、それはそうと本題だ。
某月某日、とある料理店の住居スペース。
いつもの通り環境整備に勤しんでいた炎龍ムンダーは、何やらうんうん唸る声を聞いた気がして立ち止まった。
離れた所から聞こえる声、それも唸り声となると、誰の声だか判別しにくい。一瞬灯磨が腹でも壊したのかと(男性の消化器官が女性よりも弱いのはよくあることだし)考えたが、彼なら一人で唸るよりも先にその辺りの龍に薬の在り処でも訊くだろう。気になって声の主を探すと、それは主人の私室から聞こえていた。苦しげというよりは悩んでいる様な感じである。
「入ってもよろしいですか」
「あ、はーい」
扉をノックすると、明るい声が返ってくる。やはりどこか痛めた訳でもなさそうだと思いながら扉を開けると、色の奔流が視界に飛び込んできた。
床に胡坐をかいて座る主人。珍しく例のエプロンドレスでは無く、シャツにホットパンツという組み合わせである。彼女の前には洋服ダンスを全部引っ繰り返したのではないかと思う程の量の服が敷き詰められ、床だけではなくベッドの上までも侵食していた。
…ていうか、こんなに色々な種類の服持ってたのか、とちょっと驚きつつ、服を踏まないように歩み寄る。
「衣替えですか?」
「いえ」
再び視線を床に戻し、唸りはしないものの、口を真一文字に結ぶ主人。
話を聞いてみると、今度仲のいい者同士で『私服パーティー』なるものを開くことになったのだという。
パジャマパーティーなら聞いたことがあるが、私服パーティーとはなかなか聞かない言葉である。
基本朝色の町から支給される服をそのまま着るか、多少のアレンジのみに留めている彼女たち。違う服を着ている期間が長くなると町からの援助が打ち切られる(具体的には寄付という名の家賃や税金を請求されたりするそうな。強制では無いらしいが、払うまで請求書が送付されてくるし住民としては役場に世話になった記憶が嫌というほどある為、無視し続けるのは大変居心地が悪い)為だ。朱音含め彼女の友人には『寄付』を十年分くらい前払いしても財布にダメージが無さそうな者もいるのだが、何故か皆律儀に町の支給服を着続けている。支給の服がそれなりに気に入っているのか、日々の服装を考えなくていい制服的ラクさに甘んじている為か、単に多少の出費でも払わずに済む金を払うのは惜しいというだけなのか、理由は人それぞれであろう(そしてマスターたちはその鬱憤を晴らすかのように自らの龍を自分好みに着飾らせるのであったが)。
ともあれそういう訳で、実は仲のいい友人同士であっても相手の私服のセンスは知らないということが多かったりする。別に知ってどうこうという話でもないが、ふと気になると止まらない。そういう訳で、『今度私服を着て集まってみようか』という話になったのだという。
「それはなんとまあ、素晴らしいですね」
「…素晴らしい、…か…?」
胸の前で手を合わせ、うっとりするムンダー。朱音は思わず首を傾げた。
いや、自分たちでもそれなりにいい企画だと自画自賛してはいるのだが、第三者にそこまでうっとりされる程の企画だっただろうか。
「いいじゃないですか、年頃の女の子たちらしくて」
「…………」
そういえば年頃の女の子たち、だっただろうか…とも問い返したくなるが、それを言うと自分以外の者まで巻き込むことになる為、朱音は口を開かなかった。別に今ここでそれを言ってしまった所で羽堂がにやにやしながら肘でつついてきたりかなたが泣き真似をしたりなんてことはないのだが、律儀である。長年の間に身に付いた条件反射かもしれない。
「それでマスターは、自分が着ていく服について悩んでいたという訳ですね」
飛ばしかけた思考が戻ってきた。朱音は改めて考える。
顎に指を当て、中空を眺めて、うーん…と声に出して呟く。
「…そうですよ。具体的には、…ガチで行こうか、ネタで行こうかとか」
「…ネタという選択肢がある辺りがとてもマスターらしいですね」
「ありがとうこの上ない褒め言葉です」
朱音は真顔で言った。嫌味でもなんでもなく、本気で言っているのである。
「…僭越ながら意見させて頂くと、『私服が見たい』企画なんですし、ガチもネタもなしに自然体で行けばいいんじゃないでしょうか」
「その自然体っていうのが難しいんじゃないですか…」
まあ、それはそうだ。
しかも現在ニートまがいのフリーターもどきをしている羽堂や、『戦闘系って要するに喧嘩っぱやい無職』とかいう自虐ギャグを飛ばしているかなたとは違い、朱音はきっちり労働時間の決まった店舗を持つ身。彼女らよりも『制服』でいる期間は長く、寝て起きたら寝間着から支給服に着替え、支給服を脱いだらお風呂に入ってそのまま寝間着、なんて珍しくもない。前に寝間着以外の私服を着たのはいつだったかしら(某会員制カフェで着たコスプレなどは自分のものではないので除く)、と指折り数えなければ思い出せないくらいである。そういう訳で朱音にとっては『自然体の私服』というのは少々頭の痛い問題なのである。
せっかくの機会だし、気合を入れていくか?いやいや、盛りすぎて友人たちに『気張りすぎじゃない?』と笑われても困る。ならシンプルに、とも思うが、他二人が気合を入れてきた場合に浮くのも困る。朱音さん私服は結構地味なんだあ、とか言われてカフェでのコスプレ攻勢が激しくなってしまうかもしれない。冷静に考えたら友人たちはそんなことで嘲るようなタイプでもないのだが(青いほうはともかく紫の方は後々ネタにしてきそうではあるが)、そんなことは半分くらい頭から抜け落ちている。要するにやっぱり珍しい機会にそれなりに浮かれているのだ。
「…………」
うちのマスターはそういうことを気にかけるタイプだったのか、とムンダーは思っていた。
口に出すとマスターの覚えがめでたくなくなりそうなので言わない。賢明な判断である。
「だったらいっそ電話して服装をリサーチ…とも思ったんですが、ダメです、それは楽しくない。何が楽しくないって、当日お二人の私服を初見で楽しめない自分が楽しくない」
「…………」
うちのマスターはそういうことを気にかけるタイプだったよね、とムンダーは思っていた。
口に出してもそうですが何かとか言われそうだし、今更なので口に出さなかった。賢明な判断である。
「そうだ。いっそいつものドレスからエプロンだけ外していけば着易くてそれなりに見栄えが良くて派手でも地味でもない!」
「ダメですマスター」
いいこと思いついた、と例の青いドレスを手に掛ける主人に、ムンダーがものすごい早さで突っ込みを入れた。
さっとハンガーを取り上げ、笑顔のままでむっと睨む。器用だ。
「確かに似合うでしょうし、エプロンドレスからエプロンを外せば別の服です。髪型を変えればそれはそれは新鮮な印象になるでしょう。ですが、そんな無難に逃げて、何の為の祭りですか!貴女はそういったことを見失うような女性ではないと思っていたのに…!」
「!」
漫画なら、ガーン、という効果音と共に背景に薔薇の花弁でも散っていただろう。演出担当は勿論どこぞの炎龍。

朱音はふらりと床に崩れる。上半身を傾けたまま顔を上げ、熱い視線でムンダーを見つめた。
「そうか…ムンダー、私は間違っていました。考えている内に恥を恐れ、無難と言う安寧の地獄に逃げ込もうとしていた…しかし、目が覚めました!そうですね、祭りですもんね!どうせ阿呆なら踊らねば損!」
ムンダーは優しい目で朱音を見る。
元から柔和な顔つきの彼女だが、今は後光が見える程だ。
彼女は頷き、そっと白く柔らかな手を主人へと差し出す。
「解ればいいのですよ、マスター。さあ、私が手伝いましょう。一緒に一番オシャレな着こなしを探すのです」
「はい、先生!」
朱音は、差し出された手とムンダーの顔を交互に見つめ、笑った。迷わずにその手を取り、立ち上がる。
手に手を取り、見詰め合う二人。漫画ならスポットライトが降り注ぎ以下略。
二人はしばらくそうやった後気が済んだのか手を離す。
「これとかどうですかね」
「それならこれを重ねるのとか…インナーはフリルがついたのを着て、チラ見せを狙うとかも定番ですが可愛いと思います」
真顔で会話を続ける二人。
さっき出現した謎の空間の名残など欠片も無い。
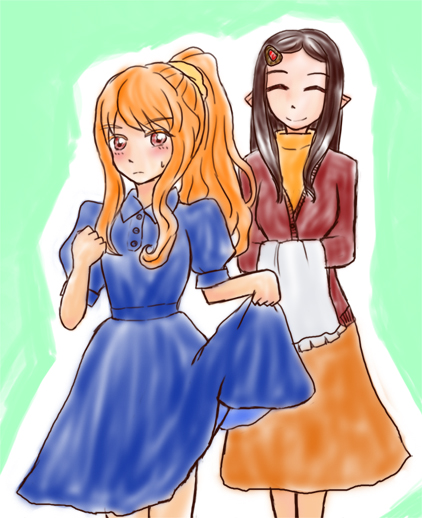
「………何なんだ、あいつら」
開きっぱなしのドアの向こう、廊下の隅っこ。
飲み物を取りにいこうと自室の扉を開けた瞬間に物語が始まってしまい、なんとなく一部始終を眺めていたポコスは、思わず一人呟いたのであった。
因みにムンダーは彼に判断を仰ぐという方法も考え、しかし恐らく彼は主人が何を着ても「いい」としか言わないだろうと思ったので敢えて登場人物から除外したのだ。ムンダーの知能的判断が輝いている。
後日、意気揚々と出かけていく朱音を、ムンダーはいつまでも見送っていた。
その顔にはコーディネーターとしての自信が感じられ、心なしか肌までつやつやしているように見える。
朱音は人に着せるのが好きだが自分が着るのも悪くないタイプ。ムンダーは自分が着るのも悪くないが人に着せるのが好きなタイプ。全く同じことを言っているように見えて、それぞれ微妙にニュアンスが異なるというのがお判りだろうか。このタイプの二人の相性が悪いわけがないというのもお解りいただけるであろう。
「…………」
「炎姉さんはそんなタイプだからイマイチ目立たないんだろうなとか思ったけど言いませんでしたね。褒めてあげましょう」
「お、おれそんなこと思ってないよ!?」
出かける主人と見送るムンダーを、更に後ろから眺めていた二人。
淡々と言うだけ言って踵を返すエゲリアを、灯磨が泡を食って追いかける。
111番地の名裏方、ムンダー。
彼女が表舞台に出るまでは、もう少し時間が必要そうである。